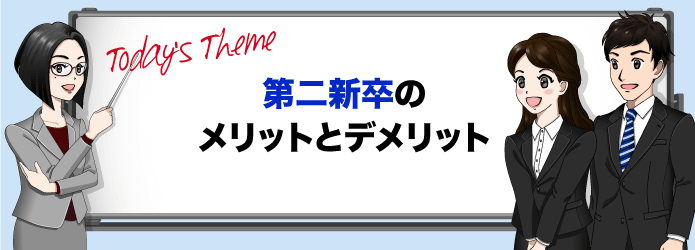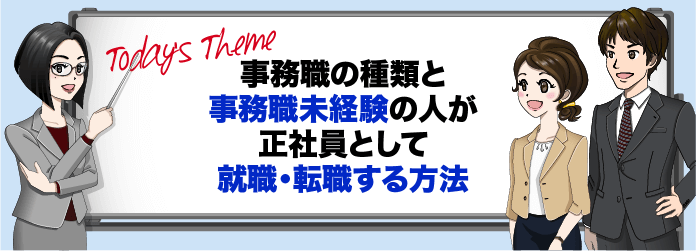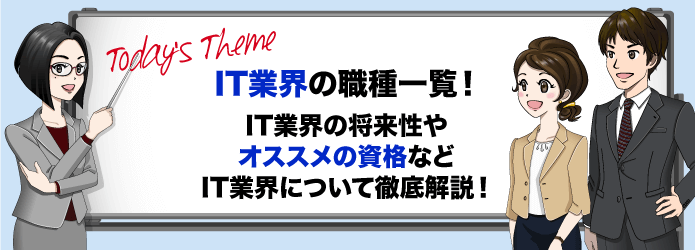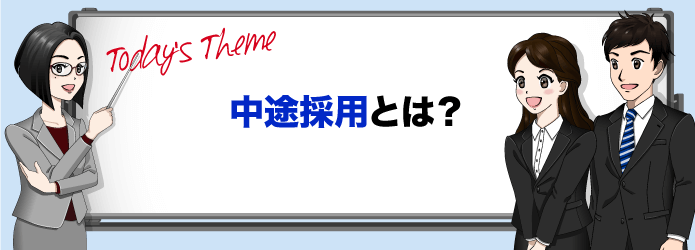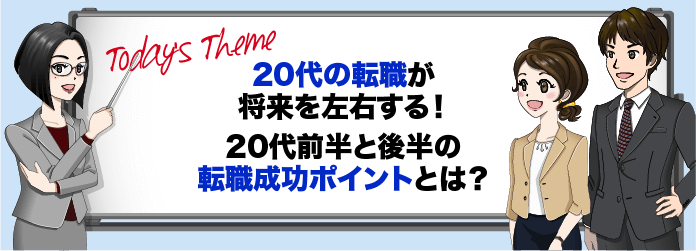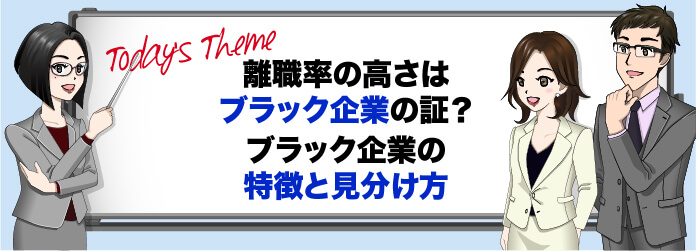
ブラック企業とはよく聞く言葉ですが、「実際にどんな会社のことをいうの?」と問われると、定義があいまいでわかりにくいですよね。
長時間労働とパワハラによる過労死や、自腹購入の強要、理不尽なノルマを課して自主退職に追い込むなど、ブラック企業による弊害は社会問題のひとつとなっています。
就職や転職をする際に、できればブラック企業には就職したくないですよね。そこで今回は、ブラック企業の定義や特徴、ブラック企業の多い業界などについて解説します。
離職率や求人票でブラック企業を見分ける方法も紹介するので、是非参考にしてください。
 石峰朱実
石峰朱実 “ブラック企業”という単語をよく耳にしますね。ただ、それはどんな企業かを明確に説明できる人は少ないのではないでしょうか。自分の希望に合わない、自分が辛かった、だからブラック企業だ、と言い出すと意味合いが違ってしまうので、注意したいところです。とはいえ、できるだけ従業員を大切にしてくれる企業でイキイキと永く働きたいと多くの方が思うでしょう。そのための失敗しないチェックポイントを挙げていますので、参考にしてみてください。但し、自分の思い込みで決めつけず、応募時、面接時に不安な点や不明な点はしっかり質問することも大切です。
目次
ブラック企業とは?ブラック企業の定義を解説
ブラック企業には、はっきりとした定義がありません。厚生労働省のホームページでも「ブラック企業に明確な定義はない」としています。
つまりブラック企業とは、労働法などの法律に抵触する内容がふくまれているなどコンプライアンス意識が低く、過酷な環境で従業員を働かせる企業の総称として使われます。
具体的には、サービス残業や過剰なノルマの常態化、セクハラやパワハラの放任、法令に抵触する営業行為の強要などです。
このように明確な定義はないものの、「企業の利益を最優先し、従業員の人権が守られない」ことがブラック企業の大きな特徴といえるでしょう。
またブラック企業には以下の3つのタイプがあるといわれます。
- 使い捨て型
長時間労働やサービス残業で従業員を追い詰める
- 選別型
大量に採用した後、過酷なノルマを課せてクリアできた人だけを残す
- 無秩序型
パワハラや退職拒否などなんでもあり
ブラック企業に入ってしまうと、会社に妨害されて簡単に退職できないこともあります。
入社前にブラック企業だと見極める力をつけ、入社を避けることがベストと言えるでしょう。
ブラック企業と言われる会社の特徴14個

それでは、ブラック企業と言われる企業の特徴を見てみましょう。
以下で紹介する14個のうち、該当する数が多いほどブラック度が高いので、あなたが今働いている会社や、これから応募する企業が当てはまるかどうか確認してみてください。
1. 離職率が高い
ブラック企業としてまず思いうかぶのが、離職率の高さ。
離職率とは「会社に入社した人のうち何人辞めたか」の割合です。
一般的には期初から期末までの1年間で算出しますが、「入社3年後まで」のように、一定期間で離職率を算出するケースもあります。
たとえば、3年後離職率が60%を超えていれば、入社した人の6割以上が3年後には辞めていることですね。
「そんなにたくさんの人が辞める会社があるの?」と思うかもしれませんが、実際にそれより高い離職率の会社も存在します。
またブラック企業の特徴として、若手が育たず30代~40代の中堅社員が極端に少ない、など社員の年齢層に偏りが見られます。
2. ハローワークにいつも求人が出ている
ブラック企業は離職率が高く、常に人手不足になりがち。
そのため、人員補充のため常に募集をかける必要があります。
しかし企業が求人サイトに広告を載せるのは大変なコストがかかり、求人掲載料の相場は4週間で20万円、またはそれ以上になることも。
それに比べハローワークは公的機関のため、求人掲載は無料です。
そのため掲載企業が多く、中にはブラック企業も含まれているかも知れません。
いつ見てもハローワークに求人が上がっているような企業は、ブラック企業の可能性も否定できません。
3. 大量募集をかけている
新しい事業の立ち上げで人手不足のとき、企業は大量採用を行います。
大量採用はコストがかかるものの、研修や教育を一度で行えるメリットがあります。
たとえば、新店舗を増やすための「オープニングスタッフ」などがそれにあたりますね。
ですが事業の拡大はないにもかかわらず、大量募集をかけている会社には注意が必要です。
はじめから大量に辞めることを見越して、人を集めていると考えられるからです。
大量に採用した後、ノルマに耐えきれなかった人を辞めさせるブラック企業「選別型」の可能性があるでしょう。
4. 契約社員など非正規雇用の社員が多い
アルバイトや契約社員など「非正規雇用の割合が高い」のも、ブラック企業の特徴の一つです。
なぜなら非正規雇用の方が、採用コストや人件費がかからない他、会社の経営が悪くなればすぐに切れるという理由があるからです。
またブラック企業は高い離職率から、正社員が定着しないという理由も考えられますね。
非正規雇用が多ければ、トラブルやクレーム処理など責任のある仕事はすべて正社員に任されます。
正社員の数が少なければ、一人が抱える業務は増え、結果としてサービス残業や休日出勤を強いられることになります。
5. 採用のハードルが低く即日採用・即日出勤
とにかく人手が足りないのがブラック企業の特徴。
早急に人材を確保したいので、よほど条件が悪い人でなければとりあえず雇おうと、採用のハードルを低くしています。
そういったブラック企業は「常に人手不足」「会社に問題があり、急に退職が出る」「採用が適当な会社は入社後も社員一人ひとりのことを大切にしない」という問題点があります。
なかなか採用が決まらなかったのに、一回の面接で楽に合格できた場合には注意が必要です。
6. 試用期間が終わらない
試用期間終了の明確な条件がない、試用期間終了のノルマが過酷過ぎていつまでたっても達成できないなどの理由により、試用期間が延々と続きます。
その結果、いつまでも試用期間中の安い給与で働かされることになるのです。
7. 雇用条件明示書・雇用契約書を発行しない
雇用契約書とは、使用者と労働者の間の仕事における取り決めを書類にしたもの。
契約期間、就業場所、業務内容、始業・終業時間、休日、有給休暇、賃金などが記載されていて、雇用主と労働者の間で賃金トラブルなどが起こることを防ぎます。
ただし、人手が足りない規模の小さな会社では、雇用契約書の発行がきちんと行われていない場合も。
そのときは労働条件通知書などの書面を求めれば、たいていの会社は応じてくれるでしょう。
もし書面の発行を拒むのであれば「本当の労働条件を知られたくない」など、不都合な事情があるのかもしれません。
労働条件を明示しなかったり、書面で発行することを拒否する会社は、ブラック企業である可能性があります。
8. 長時間の残業を強いられる
36(サブロク)協定では、勤務延長時間の限度(休日労働の時間数を含めない)を1か月45時間、1年間360時間としています。
これよりも多く残業をさせられる、もしくは残業せざるを得ない就業環境である会社はブラック企業の要素があると言えるでしょう。
時間外労働と36(サブロク)協定について
労働基準法第32条で定められている労働時間は、1日8時間、1週40時間、第35条では週1回休日を取ることとしています。
しかし第36条では、条件さえ守れば上記の時間を超えた労働が認められています。
「労使協定をし、行政官庁に届け出た場合においては、32条、35条の規定にかかわらず、その協定の定める範囲で労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる」
つまり行政官庁へ届け出れば、時間外労働も休日出勤もOKなのです。
そして「その協定の定める範囲」、残業や休日労働を行う場合の上限を決めているのが、36(サブロク)協定です。
ちなみに、36(サブロク)協定の使用者が、36(サブロク)協定を締結・届出しないで(もしくは協定の範囲を超えて)、時間外労働や休日労働をさせた場合には、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
9. 給料や残業代などの手当がきちんと支給されない
不当な低賃金労働、給料が給料日に支払われない、残業代はもちろん休日出勤やその他の手当を支払わないなど、給料をきちんと支払わないブラック企業もあります。
また、実際は残業しているけど、タイムカードは定時で記録するのが暗黙のルールとなっているブラック企業も少なくありません。
ちなみに給料の未払いは労働基準法第24条に違反する行為です。
もし今働いている会社で給料の未払いに悩んでいるようなら、労働分の給料や手当が支払われていないことを証明する資料(タイムカード、業務日報、通帳など)を用意して、会社に支払を求めましょう。
それでも支払いが行われなければ、労働基準監督署や弁護士に相談するのも解決方法のひとつです。
10. 基本給に残業代が含まれている
「未経験でも月給30万円!」
一見すると「未経験で月給30万円支給される」という条件は、とても好条件で魅力的な会社に感じるかもしれません。
ですが、そこには一定時間分の残業代(みなし残業)があらかじめ含まれており、基本的に残業をしなければ仕事が終わらない業務であることが多いです。
さらに悪質なブラック企業なら、みなし残業代以上の残業を求められる場合も。最悪の場合、みなし残業分を超えた残業代が支払われないこともあります。
※労働基準法に則り、みなし残業制を取り入れること自体は違法ではありません。
11. 書類や備品の紛失など事務処理や管理がずさん
書類や備品の管理ができていない会社は、コンプライアンスの意識が非常に低いブラック企業です。
面接時に会社や事務所を訪れる機会があれば、ぜひ机や書棚、事務所全体がきちんと整理されているかチェックしてみてください。
もし書類や備品が散乱して整理ができていない事務所は、コンプライアンスの意識が低いブラック企業の可能性があります。
こういった企業は、採用されなかった場合に、履歴書をきちんと処分、または返送してくれない可能性があるので要注意です。
12. ノルマを達成できなかった従業員に自費で購入させる
保険や服、飲食店の売上、お中元・お歳暮など、目標達成できなければ自費で自社製品を購入させる会社があります。
高額な値段にもかかわらず、断れない雰囲気で、つい購入させられてしまう人が多いようです。
仮に「契約時にノルマ達成できなかった場合は罰則」という会社の規則があったとしても、労働基準法では、一定額の違約金や損害賠償を約束させることを禁止しています。
販売ノルマの設定自体に問題はありませんが、インセンティブの部分等は別として、ノルマが達成されなかった場合に給与を下げたり、商品の買取を強制するのは違法です。
「ノルマを達成できなかった自分が悪い」という従業員の心理につけこむのも、ブラック企業の特徴でしょう。
13. 利益が上げられなかった社員を自己都合退職に追い込む
たとえば、営業がはじめてという新人に飛び込み営業をさせるとします。
会社側は新人にもかかわらず過酷なノルマを設定。通常ならばもちろん達成できません。
すると達成できない新人は、会社に必要ないと判断され、社員自ら会社を辞めるように圧力をかけられます。
上司の目の前で尋常じゃない件数のテレアポをさせられるなど、精神的に追い詰めて、自分から辞めるように仕向けるのです。
14. 会社を退職できない
ブラック企業は、待遇や職場環境の悪さから退職する社員が後を絶ちません。
そのため人材の流失を防ごうと「辞めるんだったら、代わりを探してこい」「お前を雇うために支払ったお金を返せ」と脅す、退職妨害が横行しています。
そもそも労働者が会社を退職するのは自由であり、民法では「2週間前に退職を申し入れれば問題ない」とされています。
ブラック企業から退職を阻止されたときは、こちらのページを参考にしてください。
入社前にブラック企業を見分ける10の方法
せっかく苦労して転職活動をしたのに、「転職先がブラック企業だった!しかも辞めさせてもらえない!」といったことにならないよう、求人サイトの記載内容や外部の情報から、入社前にブラック企業かどうか見分ける方法を10個紹介します。
- 求人情報で常に社員の募集をしている
求人情報サイトをいつ見ても出てくる企業は、離職率が高く定着しない可能性が高いです。
パワハラな上司がいたり、当たり前のサービス残業、ノルマが厳しい可能性があります。 - 新卒者の離職率が3割を大幅に超えている
離職率の調べ方は、就職四季報の「新卒入社3年後離職率」を参考にしましょう。
新卒の3年以内の離職率は約3割なので、3割を大幅に超える場合は注意です。 - 口コミサイトに良くないコメントが書かれている
口コミサイトは、Lighthouse(旧カイシャの評判)、転職会議、キャリコネ、openwork(旧Vorkers)などが有名です。
悪い評判を多く知りたい人は、転職会議がオススメです。 - ブラック企業大賞にノミネートされている
ブラック企業大賞にノミネートされている場合、企業に問題があるか、上司によるものか、内容もチェックしましょう。
また掲載後、改善されているかどうか、インターネットで調べるとよいでしょう。 - 給与が異常に高い
「月40時間の残業代を含む」など明記はされているものの、明記の時間以上の残業をしても追加で時間外手当てが出ないところがあります。
また、「未経験でも頑張れば1年で年収500万円!」と高い報酬をアピールする企業もありますが、相当厳しいノルマを課せられる可能性があるので要注意です。 - 「未経験歓迎」「学歴不問」「年齢不問」など応募対象のハードルが低い
ブラック企業は離職率が大変高いです。人手も足りないし、どうせ定着しない。
要はハードワークに耐えうる人なら誰でもよいので、応募対象のハードルを下げて募集することも多くあります。 - 精神論や根性論が多い
ブラック企業の説明会や面接に訪れると、「やる気」や「努力」などの抽象的な言葉が飛び交っています。
一見耳触りよく聞こえますが、精神論だけで従業員を動かそうとする会社は危険です。
「頑張る=長時間勤務」と勘違いし、労働者を追い込む可能性があります。 - 「若い人材が活躍中!」を強くアピールしている
求人情報で若い人がたくさん働いていることをアピールする会社は、人が定着しないため、ベテランがいないだけの可能性があります。
なぜ若い人が活躍できるのか、面接時に確認すると安心です。 - 面接官の服装が整っていない、態度が悪い
たとえば、ファッション業界でもないのに見た目が派手で、チャラチャラしているような人が面接官として現れた場合は要注意。
また清潔感の有無もポイントです。表情が暗い、目に活力がない場合など、長時間労働で疲れているせいかもしれません。
威圧的な態度、圧迫面接がないかも気にかけておきます。 - 深夜まで灯りが灯っている
飲み会の帰りに通ったら灯りがついていた、という場合、深夜におよぶ残業が頻繁にあるブラック企業かもしれません。
繁忙期かもしれないので一概には言えませんが、いつ見ても明かりが灯っている場合は気をつけましょう。
ブラック企業が多くなりがちな業界6つ
これから就職・転職を控える人なら、ブラック企業が多い業界は避けたいですよね。
ブラック企業が多い業界の共通点は、「慢性的な人手不足」「個人を相手にした仕事」「利益率が低い」「競争率が激しい」です。
これらが当てはまる業界として、つぎの6つを紹介していきます。
ブラック企業が多い業界
- 飲食サービス業
- 宿泊業
- 保険業
- 不動産業
- IT業界
- 介護職
 石峰朱実
石峰朱実 上記の業界の中にも、労働環境のよい「ホワイト企業」と呼ばれる優良企業はたくさんあります。また時代や社会情勢によっても、業界ごとの離職率は常に上下します。
大切なのは業界の動向を知りつつ、その企業自体がブラックかどうかを見極めることですね。
営業時間外の業務量が多い「飲食サービス業界」「宿泊業界」
労働時間の長さだと、人手不足による超過労働時間、サービス残業、ワンオペ(※ワン・オペレーション)問題、売上ノルマなど問題が山積みの飲食サービス業。
とくに店舗に正社員が一人だけだと、責任が一人にのしかかり、売上の重圧がプレッシャーになることも。
また長時間労働で知られるのが、ホテルや旅館など宿泊業です。ホテル業務は常にお客さまと接することから、知らずにストレスが溜まりがちに。
さらに長時間の立ち仕事で身体的にも負担がかかる仕事です。違法なサービス残業で本来支払われるべき手当が出ないことも少なくありません。
ワンオペ問題とは
1人で店を任されることをワンオペといいます。1人なので、休憩はおろかトイレにも行けない、強盗に狙われやすい、忙しくなった場合十分な対応ができずクレームになるなどの事態が発生するため問題となっています。
個人ノルマが厳しく激務化しやすい「保険業界」「不動産業界」
ブラック企業というと、個人ノルマが厳しいというイメージがありますよね。
ノルマの厳しさでいうと、歩合制で飛び込み営業のある保険業(個人向け)がブラック企業に挙げられることも。
保険業がブラック企業と言われるのは、「お客様の都合に合わせるためアポイントが時間外や休日などになることもある」という業界ならではの理由もあります。
また給与は高いですが、扱う商品が高額のために高いコミュニケーション能力が必要とされるのが不動産業。
不動産業といっても仕事は多岐にわたり、とくにディベロッパーと呼ばれる土地の企画・開発をつとめる分野は花形として知られますね。
一方で、物件の販売や紹介をする不動産販売代理業は、個人ノルマが厳しく激務化しやすいです。
不動産を売るために、一日中飛び込み営業することもあるでしょう。
何度も営業をかけると断られるだけでなく時には罵倒されることもあるので、それに耐えられる精神力が求められます。
不動産業のブラック企業の見分け方としては、「インセンティブで稼ぐ」ことを強調している求人には注意が必要です。
たとえば、「固定給は限りなく低く(業務委託契約などにしている)、インセンティブで月◯◯万円稼げる!」と強調されている内容です。
そういった会社に入社すると、ノルマを達成するまで休日返上で、残業はあたりまえのブラック企業である可能性があります。
需要急増で人手不足が深刻な「IT業界」「介護業界」
IT業界は、ホワイト企業も多ければブラック企業も多いのが特徴です。
IT業界では受注した仕事が細分化される構造にあり、下請けになるほど仕事はきつくなるといわれます。
2次、3次下請けになるほど単価は安くなり、急な変更指示やトラブル、納期に間に合わせるために労働時間が長くなりブラック化しやすいでしょう。
また介護業界は、仕事内容と給与が見合ってないといわれることも少なくありません。
高齢者の介助では肉体労働が必要な場面も多く、24時間365日命を預かる仕事です。
それにもかかわらず、介護福祉士の平均年収は308万円(日本人の平均年収441万円)と低い水準で、そのため仕事内容と給与が見合っていないといわれます。
また介護職は、働く施設によって労働環境に大きく差があります。
「施設の掃除が行き届いていない」「働くスタッフが殺伐としている」などの施設は、ブラック企業の可能性があるでしょう。
厚生労働省で行われているブラック企業対策
劣悪な労働環境により、体も心も蝕まれてしまうブラック企業。現在では、国もブラック企業への対策を行っています。
雇用状況が優良な企業の情報を開示
厚生労働省が運営する「若者雇用促進総合サイト」で、新卒者の採用・定着状況や、平均勤続年数、従業員の平均年齢、所定外労働時間の実績、有給休暇所得実績等のデータが開示された優良な企業の職場情報を閲覧できます。
若者雇用促進法に則った信用度の高い企業が掲載されているので、サイトに掲載されている企業はブラック企業である可能性が低いと言えるでしょう。
ぜひ転職先を決めるときの参考にしてください。
若者雇用促進法とは
若者雇用促進法は若者の雇用の促進を図る制度で、若者が優良な企業に就職できるよう、さまざまな取り組みを行っています。
- ハローワークで一定の労働関係法令違反があった事業所の新卒求人を一定期間受け付けない
- 若者の採用・育成に積極的かつ若者の雇用管理の状況が優良な中小企業を「ユースエール認定企業」として認定する
労働関係法令に違反したブラック企業のリストを公開
同じく厚生労働省では、ブラック企業の実態を調査し、労働関係法令に違反した疑いで送検された企業のリストを、インターネット上で公表しています。
「労働基準関係法令違反に係る公表事案」で検索すると、企業名、所在地、公表日、違反法条、事案概要などが見られますよ。
また作家や弁護士などが選んだ「ブラック企業大賞」も有名です。
こちらは、長時間労働による過労死の事例や、上司によるパワハラ被害の詳細など、企業名と事案概要が確認できます。
では、厚生労働省が公表している「労働基準関係法令違反に係る公表事案(平成29年6月1日~平成30年5月31日公表分)」から、ブラック企業の事例を一部紹介しましょう。
- 埼玉県さいたま市B社 労働者10名に、2か月間の定期賃金合計約200万円を支払わなかったもの
→H29.3.2送検 - 東京都港区C社 労働者2名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの
→H28.12.28送検 - 愛知県岡崎市D社 約6か月以上の休業を要する労働災害について、虚偽の記載をした労働者死傷病報告を提出したもの
→H29.3.21送検
※参照)「労働基準関係法令違反に係る公表事案(平成29年6月1日~平成30年5月31日公表分)」
また公的機関であるため、求人広告の費用が無料でありブラック企業も求人を出しやすいといわれるハローワークですが、厚生労働省は労働条件が悪い企業からの求人をハローワークで拒否できる制度を拡充する方針もあります。
ブラック企業クイズ!よく耳にするあの行為は違法?違法じゃない?
突然ですが、ここでブラック企業クイズ!企業で働いていた人なら体験したことがある「これって労働法違反?」と思われることが、違法か違法ではないかをクイズ形式で紹介します。
 石峰朱実
石峰朱実 ではさっそく問題です。
繁忙期だから1か月まるまる休みがなかった!
これって違法?違法じゃない?

これは違法でしょう。違法じゃなきゃ困る!
 石峰朱実
石峰朱実 正解!これは違法です。
労働基準法では、原則として週に1日は労働者に休日を与えることになっています。
例外的に、週に1日以上の休日が難しい場合には、4週間で4日以上の休日を取ります。
ちなみに上限の労働時間は、1週40時間、1日8時間ですが、労働者9人以下の商業・サービス業関連は1週44時間、1日8時間となっているんですよ。

よかった。休日がないなんて、耐えられないです!
 石峰朱実
石峰朱実 ではつぎの問題。
海外旅行と会社の繁忙期が重なって有給を断られた!
これって違法?違法じゃない?

きっと「繁忙期」っていうところがポイントなんですよね。
でも海外旅行のキャンセル料も惜しいし…違法、だったら嬉しいな。
 石峰朱実
石峰朱実 残念ですが、違法ではないのです。
有休は、その会社の繁忙期など業務への影響が認められるような特別な場合以外は、請求した時期に取得できます。
企業側には時期変更権というものがあるので、業務に影響が出ると思われることから、有給の請求を断っても違法ではなく、他の時期に与えることができます。

いつでも好きなときに取れるわけじゃないんですね。
 石峰朱実
石峰朱実 そうですね。企業も従業員もお互いのことを考えて働きましょう。
以上のことは、「e-ラーニングでチェック!今日から使える労働法」で確認できます。
今働いている会社で「おかしいな?」と思うことがあったら調べてみてもいいですね。
【まとめ】ブラック企業の特徴を知って企業を見極めよう
今回はブラック企業の特徴や見分け方についてご紹介しました。
ブラック企業に明確な定義はありませんが、特徴を知ることで「この会社ブラック企業かも?」と気づくきっかけになるのではないでしょうか。
またこれから転職を考えている人は、応募先の会社情報をしっかり調べましょう。
「入社して嫌なら辞めればいい」という考え方もありますが、「辞めるなら代わりを連れてこい」など、退職妨害を行うブラック企業もあるので注意が必要です。
「次の転職は絶対失敗したくない」という人は、プロの目で企業を見極めてもらう方法があります。
転職エージェントを利用すれば、ネット上ではわからない、会社の社風や職場環境や社風などの情報を担当者から教えてもらえます。
その他、応募書類の作成や求人の選び方についてもアドバイスがもらえるので、「ブラック企業を避けたい」という人は利用してみるとよいかもしれません。
転職エージェントをはじめて利用するなら、dodaやマイナビエージェント、リクルートエージェントといった大手エージェントサービスが利用しやすいでしょう。
- 監修者:石峰朱実(キャリア・コンサルタント)

- 各種学校、公共事業にて主に就職支援を担当。また転職エージェントでの面接指導にもあたっており、人材業界での10年の勤務経験も含め、就転職支援では20年超のキャリア。>>詳細はこちら